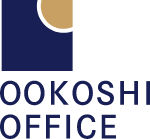Blog労務ブログ
就業規則とは?知っておくべき基礎知識を社労士が解説!
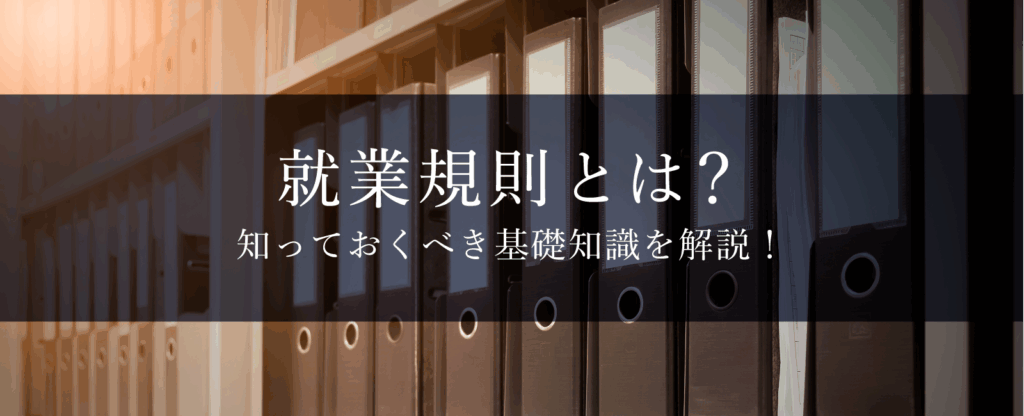
就業規則とは?
就業規則とは、従業員が会社で働くうえで守らなければならない労働時間や服務規律などについて定めた「職場のルールブック」です。
労働基準法に、就業規則に記載する内容や、作成・変更する際の手続などについて定められています。本記事では、足立区の社労士 大越事務所の大越が、会社が知っておくべき就業規則の基礎知識を解説します。
就業規則の作成義務
「常時10人以上の労働者を使用する使用者(事業場)」は、就業規則を作成する義務があります(労働基準法第89条)。
就業規則を作成する義務があるにも関わらず、作成を怠った場合には、会社に対して「30万円以下の罰金」の罰則が定められています(労働基準法第120条)。
参照:厚生労働省「就業規則を作成しましょう」
「常時10人以上」であること
常態として雇用している人数をいいます。
例えば、常態として従業員が9人就業しており、繁忙期にスポットで1人増員する場合は、就業規則の作成は不要です。
「労働者」を使用していること
「労働者」とは、雇用形態に関わらず、正社員・アルバイトなどを含みます。
例えば、正社員が2人、パートが8人いれば、就業規則の作成は必要となります。
就業規則に記載する内容
就業規則に記載する内容は、大きく分けて「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の2つがあります。
絶対的必要記載事項とは、労働基準法により、必ず記載しなければならない内容のことで、以下3つが該当します。
これらの内容が記載されていない就業規則は、適正な就業規則として認められません。
➊ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交代制の場合には就業時転換に関する事項
❷ 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
❸ 退職に関する事項(解雇の理由を含む)
一方、「相対的必要記載事項」は、定めをする場合には記載しなければならない事項のことです。
以下8つが項目します。
➊ 退職手当に関する事項
❷ 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
❸ 食費、作業用品などの負担に関する事項
❹ 安全衛生に関する事項
❺ 職業訓練に関する事項
❻ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
❼ 表彰、制裁に関する事項
❽ その他全労働者に適用される事項
なお、上記に挙げた内容以外にも、「任意記載事項」として就業規則に盛り込むことができます。
例えば、採用手続や試用期間などに関する内容です。

就業規則作成・変更の手続
就業規則を作成・変更する場合、次のような手順で進めます。
➊ 就業規則の案を作成(変更)する
❷ 従業員代表者を選出し、意見を聴く
❸ 労働基準監督署に届出をする
❹ 社内で周知する
以下、具体的にご説明します。
❶ 就業規則の案を作成(変更)する
就業規則の作成(変更)は、自社で行うか、または専門家(主に社労士)に依頼するかの方法があります。
自社で作成(変更)する際は、汎用的な就業規則の雛形を活用するケースが多く見られますが、そのまま利用すると、会社の実態にそぐわない内容になり、労使間でトラブルが発生しやすくなります。
例えば、実態は賞与を支給していないのに、就業規則には「毎年6月及び12月に支給する」と規定しているケースなどです。
汎用的な就業規則の雛形を活用する際は、実際の労働時間や賃金等の労働条件、職場のルールなども踏まえ、実態に沿った内容とすることが重要です。
❷ 従業員代表者を選出し、意見を聴く
就業規則を労働基準監督署へ届出をする前に、従業員代表者から作成・変更した就業規則に対する意見を聴き、その意見を反映した「意見書」を作成します(労働基準法第90条)。
仮に、就業規則の内容について異論・反論があっても、手続上は問題無く、労働基準監督署に届出しても受理されます。
つまり、「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味で、同意を得ることまで求められている訳ではありません。
もちろん、従業員代表の意見については、出来る限り尊重することが望ましい、とされています。
❸ 労働基準監督署へ届出をする
就業規則を作成(変更)したときは、管轄する労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
その際、作成(変更)した就業規則と共に、2で作成した「意見書」も届け出る必要があります。
なお、同じ会社でも複数の支店(事業場)がある場合は、支店毎に管轄する労働基準監督署へ届け出る必要があります。
❹ 社内で周知する
就業規則は、見やすい場所やイントラネット上への掲示・備え付け、書面の交付などの方法で、従業員に周知する必要があります(労働基準法第106条)。
周知を怠ると、「就業規則は無効」と判断した裁判例(フジ興産事件/最高裁判所平成15年10月10日判決)があるため、ご注意ください。
就業規則作成の効果
前述のとおり、従業員が常時10人未満の会社は、法律上就業規則を作成する義務はありませんが、
就業規則は以下のような効果があるため、常時10人未満の会社でも作成をお勧めします。
- 休日・休暇、賃金、休職制度、副業・兼業制度、定年制などの労働条件を
明文化するため、従業員が安心して働ける環境を整えられる。 - 従業員の行動規範や禁止事項を明確にし、職場の秩序を維持する。
- 懲戒処分や退職などのルールを明確にし、労使間のトラブルを防止することができる。
まとめ
就業規則は、労使間のトラブルを未然に防ぐための重要なルールブックです。
従業員が安心して働ける環境を整え、会社の持続的な成長に繋げるために、適切な就業規則の整備をお勧めします。